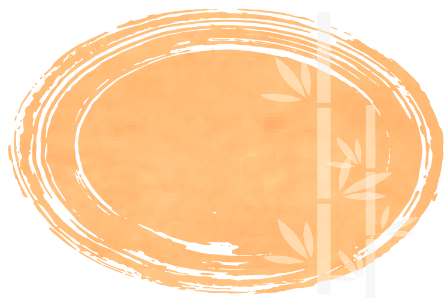
剣術、棒術
居合術、手裏剣術
タイ捨流兵法

タイ捨流兵法とは、戦国時代の肥後(熊本県)の武将丸目蔵人が剣聖上泉伊勢守信綱に新陰流を学んだ後、創始した流派である。捨て身を基本とし、上下斜めからの截合いを要としている。殺人刀の技法と、弱よく強を制する、剣術と体術が見事に調和した活人剣を含み、さらに、修行と道理を説いた保寿剣の哲学を持つ、名流中の名流。
流名「タイ捨」の由来
「タイ捨」とは、漢字で置き換えた場合、大・太・体・待などの偏った意味にとらわれてしまうおそれがあります。広義の意味を含む言葉本来の言霊として、これらを捨てた「自在の境地」を表した名が「タイ捨」なのです。
これは師上泉伊勢守直伝新陰流の旨とする「懸待表裏(けんたいひょうり)、一隅を守らず」にある通り、人は時として争いの中で一撃を持って懸かることのみに囚われ易く、またはある人は相手の働きを待って仕掛ける待の技に固執し易いため、心の自在さを失ってはならないと心法極意が述べられているわけです。
タイ捨流兵法はこの「懸待表裏」を学び、ついにはそれを捨て去った「捨」を極意とします。この「自在の境地」を流祖丸目蔵人は「タイ捨」と開眼されたのです。
流祖は剣術をはじめ、長刀(なぎなた)、槍、馬、手裏剣等の二十一流に通じた人であると同時に、文化人としての素養の高さも兼ね備え青蓮院流書道免許を持っていました。技名が記述された現存する直筆伝承の文字には流儀に携わる者には一見しただけで技の心に参入できる程の意味が込められています。現存する自筆伝書(青蓮院流書道免許)に記述される技名。流儀にたずさわる者には、一見しただけで「技の心」に参入できるほどの意味が文字にこめられています。
二天一流(居合)

二天一流は、流祖・宮本武蔵が、晩年に熊本で完成させた兵法。宮本武蔵の父・新免無二は、實手・二刀流などを含む當理流の使い手だったが、武蔵はそれを発展させ流名を円明流に改めたという。晩年、伝えていた一刀、二刀、實手など多くの形を捨て、右手に大太刀、左手に小太刀の二刀を用いる五つのおもて「五方」の五本にまとめ上げ、その兵法理念を『五輪書』に書き表した。『五輪書』では流名は二刀一流・二天一流の二つが用いられているが最終的には二天一流になったと考えられる。後世には、二天流・武蔵流の名も用いられている。
二天一流と五輪書(ごりんのしょ)
五輪書は、宮本武蔵の代表的な著作で、地水火風空にかたどって5巻に分かれた兵法書です。二天一流は二刀流を主に使います。また一刀の時にも、片手で刀を持つ様にしています。「武士は折角二本刀を差しているのだから、討たれるときに片方の刀が使われていなかったらきっと悔しいに違いない…」と言ったそうで、これは二天一流の極意「ある物は何でも利用する」に通じます。その精神が最も発揮されたのは、鎖鎌の使い手宍戸梅軒と戦ったときであり、この時武蔵は鎖に捕らえられた太刀を投げつけ、脇差を抜いて相手を倒ました。実戦で二刀を使ったのはこれだけと言われますが、二刀流の様々な構えを考案したのは事実。
技術的な特徴は、相手の剣をぎりぎりで見切ってかわす防御と、二刀を用いて行う休みのない攻撃にあります。攻めて、攻め抜いて、相手の構えが崩れた所に渾身の技をふるうのです。









